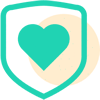椎間板ヘルニアの腰痛は安静とストレッチどちらが良いですか?
1ヶ月前から腰痛があり、整形外科で椎間板ヘルニアと診断されました。
症状としては、まだ痛みで腰が伸びず、まっすぐ立つことができません。腰を90度に曲げて歩いています。。。
横になっていれば、痛みはほぼありません。
現在生後2ヶ月の赤ちゃんの育児中で、母乳のため、カロナールと湿布のみ処方されましたが効果がありませんでした。
重いものを持つのは良くないことは認識しているのですが、赤ちゃんを抱っこしないわけにはいかず、困っています。
なるべく安静にしたほうが、回復が早いでしょうか?
それとも、少し無理をしてでもストレッチ等を行った方が良いでしょうか?
症状は腰痛でしょうか?下肢の痺れと痛みでしょうか?
腰椎椎間板ヘルニアとは、腰椎の椎体の上下をつないでいる椎間板の内部にある髄核が線維輪という周囲を固めている組織を突き破ってはみ出して神経を圧迫することで、下肢に神経痛を生じる疾患です。腰痛を伴うことも多いのですが、下肢痛がないときはMRIで椎間板ヘルニアの所見があっても痛みの原因とは考えません。
基本は安静が必要です。
治療はロキソニンなどの鎮痛消炎剤とタリージェなどの神経障害性疼痛治療薬の併用には相乗効果が期待できますし、トラムセットなどの弱オピオイドも有効です。硬膜外ブロックなどのブロック療法も効果的です。
痛みが治まれば体幹筋力を鍛えるリハビリやウォーキング、ストレッチなども良いでしょう。
これらの保存療法でも改善しなければ手術を考慮します。
繰り返す負荷や急なひねり動作、重量物持ち上げなどによる急激な椎間板内圧の上昇が原因で、椎間板の外側のドーナッツ状の組織である線維輪に亀裂が入ることで腰椎部、臀部に痛みが生じます。椎間板内部にある髄核というジェリー状の組織が線維輪の亀裂部分から神経方向に膨隆したり飛び出したりした状態が椎間板ヘルニアです。
飛び出した椎間板組織が神経を圧迫することで腰痛に加えて臀部・下肢の神経障害症状が生じます。
ベルト固定等の安静や投薬、硬膜外ブロック、神経根ブロックなどの保存療法で症状の軽減が得られる場合の方が多いのですが、神経の圧迫が強い場合や、神経麻痺症状(運動麻痺)が出ている場合には手術の適応となります。
突出したり脱出した椎間板ヘルニアが多核巨細胞の貪食により自然吸収されることが多いのですが(約90%程度)、安静や投薬、神経根ブロックなどの保存療法に関しては、その間の症状の緩和を図るためのものとなります。一般的に3~4ヶ月程度の期間の保存療法が無効な場合には手術が選択肢となってきます。圧迫が強く疼痛が強い場合や、神経麻痺症状が出ている場合にはより早期の手術の適応となります。
前屈45°の姿勢において椎間板内圧が最大値になる事が実験的に示されていますので、中腰を避け重いものを持たないようにしてください。
正確な診断には腰椎のMRI検査が必要です。
可能であれば脊椎専門の整形外科を受診してみてください。
椎間板や椎間関節に負担がかかり痛みが出るということはありますが、診断にMRI検査はされたでしょうか?
もし椎間板ヘルニアの部位がはっきりしていて、明らかに神経の圧迫されている箇所があるという場合、ブロック注射など行っていただくのもよいと思います。
激しい痛みのある間は安静です。コルセット使用なさって下さい。痛み軽減すればストレッチ、体幹筋力トレーニングなさって下さい。また、MRI検査でのヘルニアのタイプ及び重症度をご確認下さい。
安静がいいです。MRIはされていますか。
簡易ベルトなどもいいと思います。
お辛いことと存じます。
なるべく安静にしたほうが、回復が早いでしょうか?→やはり安静のほうがよいとは思いますが、可能な範囲でだと考えます。
それとも、少し無理をしてでもストレッチ等を行った方が良いでしょうか?→ストレッチやリハビリの方法や時期は、個人によって違いますので、できればMRIの施行できる清家外科での意見をきいたほうがよいように思います。
コルセットを巻いてもよいかと考えます。
今は炎症期ですので無理せず、痛みの軽減を最優先していきましょう。痛みを悪化させる動きは避けるが、完全な寝たきりは避けましょう。ストレッチは痛みが軽減してから始めましょう。カロナールの量を増やしたり他にも使える薬を主治医と相談しましょう。育児動作としては前屈を避け、台の高さ調整やサポート具を活用しましょう。
運動の開始時期や、どれくらいの強度で運動していいかは、症状やヘルニアの程度によって変わってきますので、かかりつけの整形外科の先生にきちんと確認されることをお勧めします。お大事になさってください。